
年間行事
| 月 | 行事名 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 4月 | 体育祭 | 小学校から高校までの12学年縦割りチーム4色による対抗戦。午後一番プログラム「応援合戦」が華。 |
| 5月 | 歓迎遠足 | 6年生が1年生の手を引きながら縦割りグループで行動し、皆で新1年生を迎え入れます。 |
授業参観 | 授業参観と学年別オリエンテーション。“圧倒的に個へ関わる”精道三川台の教育方針を伝えます。 | |
6年修学旅行 | 2泊3日で萩(山口)、北九州を訪ねます。明治維新の歴史、自然の驚異、日本の最新科学技術に触れます。 | |
精道さるく | 保護者の案内で学校を見学していただきます。保護者目線でのお話をしながら授業を見て回ります。 | |
ロザリオ巡礼(学年別) | 5月は“聖母月”聖母マリアへの祈りを通して、『誠実な心』の大切さを学びます。 | |
| 7月 | あじさい劇場 | 1年〜4年が演劇、5・6年は合奏を披露。 演劇では他者との関わりをフィクションの力を借りて疑似体験することができます。つまり、コミュニケーション教育の有効な手法です。無理に自己を変えるのではなく自分と演じる役柄の共有できる部分を見つけていくことによって他者と関わる術を児童たちは学んでいきます。 また、演劇は教室の学びだけでは見られない個性が発見されたり、自分を表現することで、自己肯定感を育みます。 同様のことが合奏にも言えます。 さらに、クラスの結束力も強めます。 場所:チトセピアホール |
親子レクリエーション | 1~3年生の父子と教員が沢登りやジェスチャーゲームなどを通して、親睦を深めます。 場所:国立諫早少年自然の家 |
|
| オープンスクール (園児学校体験)  | 入学希望者や一般の方に学校説明を行った後に、園児が模擬授業を体験します。 | |
| 9月 | 夏休み作品展 | 夏休み中に取り組んだ絵画や工作、自由研究などの展示会。自力で又は親子で手掛けた力作が勢ぞろいします。 |
名文暗唱 | 人々に親しまれてきた古今の名文に親しみ接することで言葉の感性を養います。初級~上級へと個々のペースに合せて約1ヶ月間取り組み、記憶力と集中力も伸ばしていきます。 | |
公開授業&学校説明会 | 次年度の入学希望者に、精道三川台小学校の教育方針をご説明いたします。その後は、授業を自由に見学できます。 | |
| 10月 | 野外教室 | 4,5年生1泊2日の合宿。「規律・協力・責任」をモットーに、野外調理やウォークラリーなどの活動を行います。 |
秋の鍛錬遠足 | 1~3年生が金比羅山や稲佐山などに向かいます。秋の季節を感じながら縦割りグループで活動し、3年生のリーダーシップを伸ばします。 | |
| 11月 | かもめ祭り | 小中高の全校をあげて行う本校独自のバザー。保護者企画の店や高学年児童の店も並び、賑わいます。また児童は清掃奉仕活動も行い、児童・保護者・教職員・地域が一致協力して当日のバザーを運営します。 |
| 12月 | クリスマス会 | イエス・キリストのご降誕をお祝いします。御ミサにあずかったあと、児童会主催でゲームなどを行い、クリスマスの楽しいひと時を過ごします。 |
| 1月 | 百人一首大会 | 低学年、中学年、高学年の3つのグループに分かれて一斉に百人一首を行います。 |
| 2月 | 児童会役員選挙 | 次年度の執行委員を選出します。 |
なわとび大会 | 学年に応じてなわとびの様々な種目に挑戦します。 各学年全員で跳ぶ3分間の「長なわ」が華。 |
|
| 3月 | 送別集会 | 児童会主催。 在校生が出し物を披露し、6年生に感謝を表し送り出します。 |
卒業論文発表会 | 6年生が一年間かけてまとめた「卒業論文」をプレゼンテーションします。 |





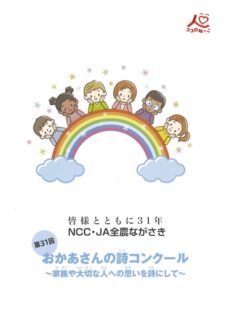


Facebookコメント